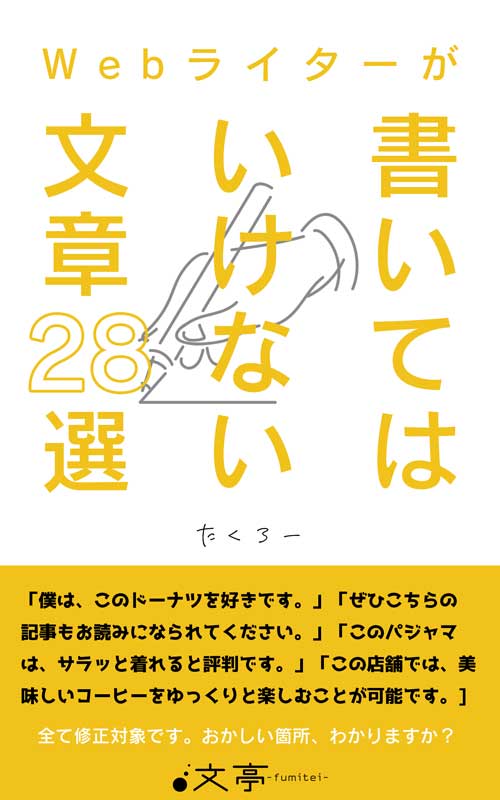羅生門の原文は、いまの時代から見ると、なんとも読みづらい文体で書かれています。
もちろんそれが味でもあるのですが、物語というものは、読みづらいものを無理に読むものではありません。
今回は『羅生門』を現代語訳にして、ストーリーの本質に関係ない描写はざっくりと削り、場面ごとに6つの章に区切りながら3,800文字にまとめました。さらに時代背景がわかる解説と、あらすじも掲載しています。
芥川龍之介の描く独特の世界観は少々損なわれているかと思いますが、どんな物語なのか知りたい方は、ぜひ当記事にてご覧になってみてください。
※羅生門は、すでに著作権が失効している作品です。よって全文独自に現代語訳にして掲載しております。
『羅生門』とは
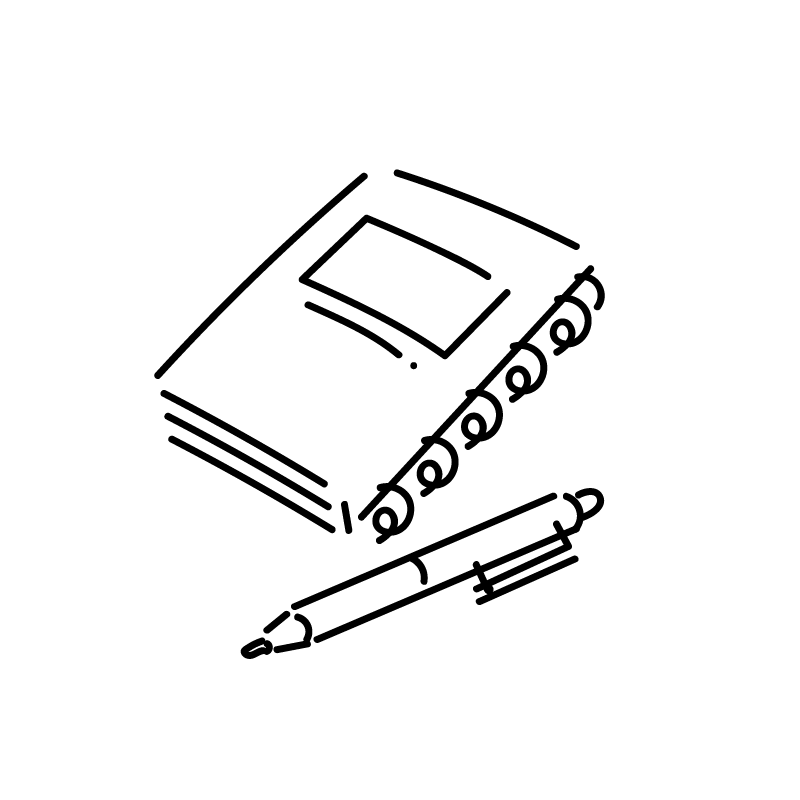
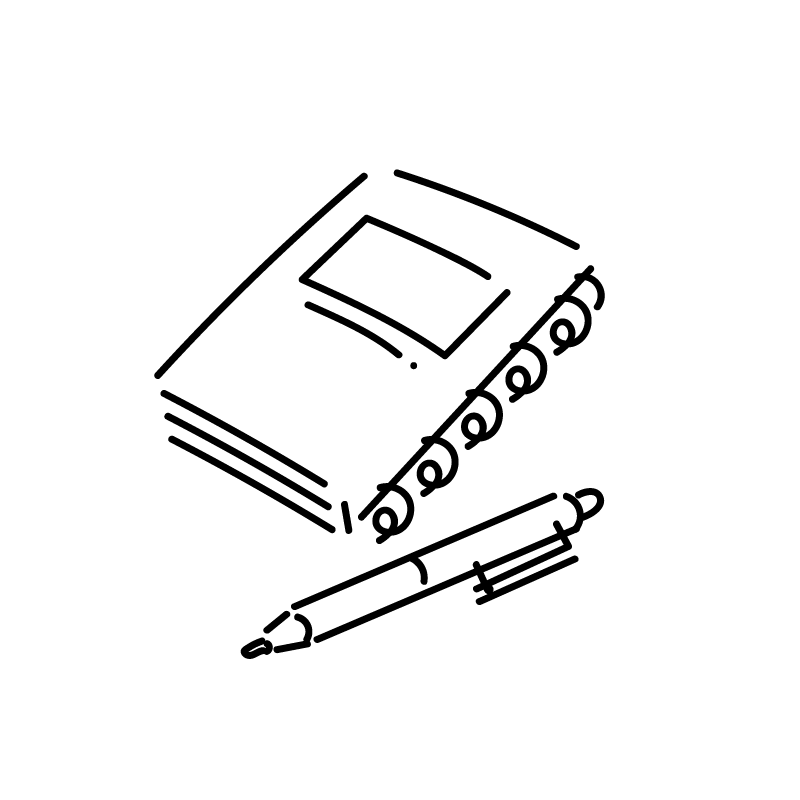
『羅生門』は、1915年(大正4年)に芥川龍之介が執筆した短編小説。彼が東京帝国大学在学中、まだ無名だった頃の執筆作品です。現在はすでに著作権が失効しており、青空文庫に収録されています。
物語の舞台は平安時代の京都。数年もの間、立て続けに地震や火事などの災害が続き、京が荒れ果てていた時代です。
羅生門とは、その平安京のメインストリートである「朱雀大路」の南端に備わっていた大きな門。その門を舞台に、主人公である下人の男と物取りの老婆、二人の心理を描いた物語です。
『羅生門』のあらすじ
主人から暇を出された下人は、降りしきる雨のなか、羅生門で途方に暮れていた。
京は荒れ果てていて、どこにも仕事はない。このままでは飢え死にするだけだが、とはいえ泥棒に身を落とすほどの決心はつかない。
羅生門の門の上にある小屋で一夜を過ごそうと決めた男は、先客である物取りの老婆と鉢合ってしまう。
老婆との問答、善悪、心変わり。極限状態が織りなす、一人の男の心理を描いた物語である。
『羅生門』を現代語訳にして3,800文字でまとめてみた
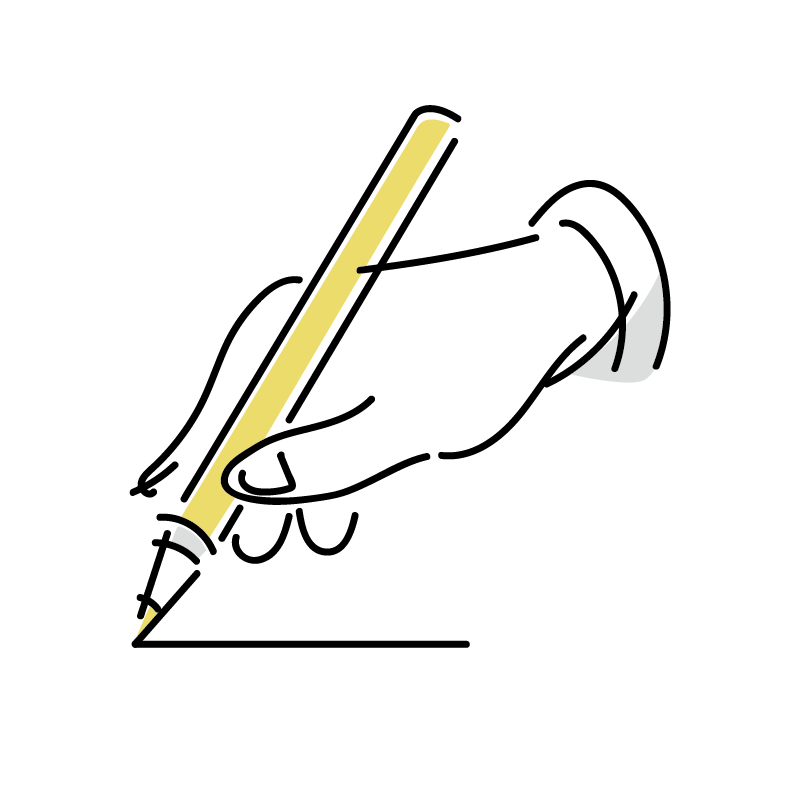
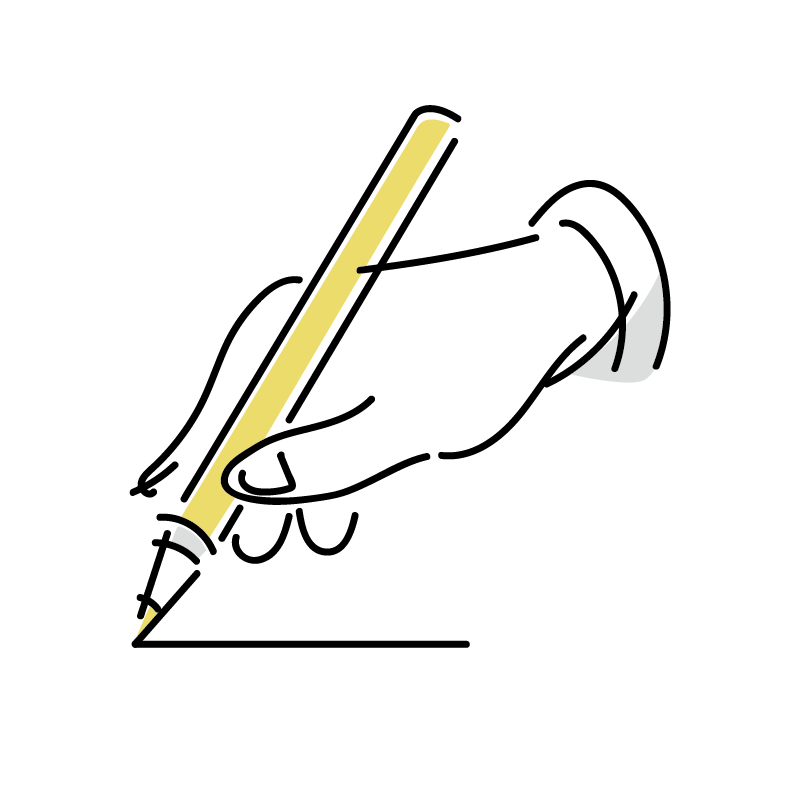
- 第一章:とある下人の物語
- 第二章:下人の逡巡
- 第三章:下人の戸惑い
- 第四章:下人の正義感
- 第五章:下人と老婆
- 第六章:下人の行方
第一章:とある下人の物語
ある日の夕方ごろ、一人の下人が、羅生門の下で雨が止むのを待っていた。
おなじく雨にうたれて駆け込んできた女性との恋が始まる……なんてこともなく、広い門の下には誰もいない。門が面しているのは、平安京のメインストリートである朱雀大路なのにもかかわらず、だ。
本来なら、ちょっとしたお偉いさんの2,3人くらい、暇そうに雨宿りしていてもおかしくない場所である。それがどうだ。いまや色の剥げてしまった円柱に、キリギリスが1匹とまっているだけである。
「さすがに誰もいないな……まぁ、当然か」
ここ2〜3年、京では地震や嵐、火事などの災いが続いて起こった。それが原因で、京全体が寂れてしまったのだ。
お偉いさん達が住む洛中でも、仏像や仏具をくだいて焚き火用の薪にして売る輩が出るほどである。それほど木も物資も足りていないのに、羅生門の修理なんて到底無理な話だ。
そんな荒れ果てた羅生門には、詐欺師や泥棒が住み込むようになった。引き取り手のいない死体(その多くは、やはり詐欺師や泥棒だったりする)を、門の上に捨てるような習慣すらできてしまった。そんな羅生門だから、日が暮れた今くらいの時間には、もはや誰も寄り付かないのである。
ちなみに人の代わりに集まるようになったものがいる。カラスだ。特に昼間は、門の上にある不憫な無縁仏をついばみにくるのだ。
しかし夕刻も過ぎた今では、そんなカラスすらもいない。
誰もいない羅生門の夕闇の中、男はひとり右頬のニキビを気にしながら、降りしきる雨をぼーっと眺めるのだった。
第二章:下人の逡巡
ここで疑問が湧く。こんなところで雨宿りをしている下人とは、一体何者なのだろうか。
実はこの男も、4日前にとうとう仕事をクビになってしまったのだ。とある主につかえていたのだが、京中が寂れた余波を受けて仕事が無くなり、突然に暇をだされて行く宛がなくなってしまった。
要するに、どうしようもなくご時世の被害者なのである。
雨宿りをしているというよりも、ただ行く宛がなく、困ってここにいるだけなのだ。
「このままだとまずい」
生きていくのなら、泥棒にでもなるしかないとは思っている。どうにもならないことを、どうにかする。それには手段を選んでいるような暇はないのだ。
だが真面目に生きてきた男には、どうにも踏ん切りがつかない。このままだと、どうにもならないことは分かってはいるが……。
下人は大きなくしゃみをすると、やれやれと立ち上がった。
京は夕方になると冷える。まずは一晩しのげる場所がなければ、明日の昼にカラスがついばまむのは我が身だ。泥棒になるような踏ん切りはつかないが、できればそれは避けたい。
どうしたもんかと辺りを見渡すと、運よく門の上の楼——高所に見張り用で設けられた小屋だ——へと登るハシゴが見つかった。
これはしめたとばかりに、腰に下げた刀がすべらないよう、下人はそのハシゴへと足をかけたのだった。
第三章:下人の戸惑い
——数分後、男はまだハシゴの途中にいた。
ハシゴがそこまで長いわけではない。どうやら楼に、生きている何者かがいるようなのだ。火を焚いており、その火が動いている。このご時世に、こんな場所で火を灯しているのは、どう考えても何かしら問題のある人物である。この際、自分のことは棚に上げておこう。
さて、どうせ死体しかいないだろうとたかを括っていたのに、こまった事態だ。不用意に見つかるのも危険だし、かといってこのままハシゴで一晩を過ごすわけにはいかない。
下人はできるだけ足音を立てないよう注意しながら、やっとのことでハシゴを登り切った。
こっそりと楼の中をのぞくと……噂に聞く通り、多くの亡骸が打ち捨てられている。火の見える範囲が狭いのが幸いしてか、そこまではっきりとはわからないが、老若男女さまざまな亡骸があるのはわかる。
そして漂ってくる臭気に思わず鼻を摘んだが、その次の瞬間、臭いのことなんて忘れてしまった。
檜皮色——暗い茶褐色だ——の着物をまとう、背が低く痩せた猿のような老婆が、一人の女性の亡骸の顔をじっくりと眺めていたのだ。
第四章:下人の正義感
——思わず息をするのさえ忘れていた。
火が灯されている以上、誰かがいることはわかっていたとはいえ……まさか老婆がいて、しかも女性の亡骸を覗き込んでいるとは何事だろうか。
そんな下人の視線には気づかず、老婆は対松を床にさすと、おもむろに亡骸の首に手をかけた。ちょうど猿の親が猿の子の虱を取るように、その女性の亡骸の、長い髪の毛を一本ずつ抜き始めたのだ。
どうやら手に沿って簡単に抜けるようだなと、冷静に考えているうちに、下人からは先ほど感じた恐怖が少しずつ消えていった。それと同時に、この老婆に対する憎悪が湧いてきたのだ。
いや違う。この老婆個人にあてた感情ではない。この世の悪に対する反感がどんどん増してきたのである。
先ほど門の下で「泥棒にでもなるしかないか」と考えていたのが嘘のようで、今の下人は犯罪を犯すくらいならば迷わず餓死を選ぶだろう。それほど、下人の持つ正義感が、勢いよく噴き出してきたのである。
老婆が何を理由に髪の毛を抜いているのかはわからないが、ともかくそれは下人にとって許すべきではない悪だ。
湧き出してきた正義感の勢いそのままに、下人は両足に力を入れてハシゴの上へと飛び上がり、刀に手をかけながら老婆の前へと歩み寄るのであった。
第五章:下人と老婆
——逃げる。
突然誰かがやってきたことに気づいた老婆は、まるで弾かれたように飛び上がった。
亡骸につまずきながら逃げようとする老婆を、しかし下人は逃さない。
「おいおい、どこへ行く」
それでも下人を突きのけて逃げようとする老婆を押し戻し、二人はしばらく、無言のまま掴み合った。
とはいえ痩せ細った老婆と、つい4日前まで主のいた下人だ。勝敗なんてわかりきっている。下人はとうとう老婆の腕を掴み、そこに捻り倒した。
「何をしていた。言え。言わないとこれだぞ。」
下人は老婆を突き放すと、刀を抜き、そのきっさきを老婆の目の前へとつきつけた。
——しかし老婆は黙ったままだ。両手をわなわなと震わせ、肩で息を切りながら、血走らせた目を見開いて下人を凝視している。
そうこうしているうちに、下人の正義感は冷めていく。後に残ったのは、ただある仕事をして、それが円満に成就したときの達成感と満足感である。つまり今、気分が良い。
「おれは検非違使の役人などではない。今しがたこの門の下を通りがかった旅の者だ。だからお前に縄をかけて、どうしようというようなことはない。ただ今時分、この門の上で、何をしていたのか話しさえすればいいのだ」
さきほどまで門の下でうなだれていた男とは思えない、堂々とした口上である。今、この老婆を切るか否かは、男の意思一つなのだ。
老婆は見開いていた目をより一層大きくして、じっと下人の顔を見守った。まぶたの赤くなった、肉食鳥のような、鋭い目だ。それから、皺でほとんど鼻と一つになった唇を、物でも噛んでいるように動かした。
「この髪を抜いてな——」
第六章:下人の行方
「この髪を抜いてな、カツラにしようと思ったのじゃ」
しわがれた声で発せられた答えを聞き、下人はそれが存外、平凡であったことに失望した。失望すると同時に、先ほど心を支配していた増悪が、冷ややかな侮蔑と一緒に心の中へ入ってきた。
下人のその態度が伝わったのであろう。老婆は口籠もりながらも、さらに続けた。
「なるほど。死人の髪の毛を抜くということは、なんとまあ悪いことかも知れん。じゃがここにいる死人どもは、皆それくらいのことをされてもいい人間ばかりじゃぞ。いまわしが髪を抜いた女などはな、蛇を10cm少々に切って干したものを干魚だといって太刀帯の陣(たてわきのじん)に売り込んでいた。疫病にかかって死んでいなければ、今でも売りにいっていたはずじゃ。それもな、この女の売る干魚は味が良いといって、太刀帯どもが欠かさず買っていたそうな。わしはこの女のしたことが悪いとは思っておらん。しなければ餓死するなら仕方のないことじゃ。だから今わしのしていたことも、悪いこととは思わぬぞ。せねば餓死するから仕方なくすることじゃ。それをよくわかっていたこの女は、わしのする事も多めに見てくれるじゃろう」
老婆がひとしきり喋っている間、下人は刀を鞘へとおさめ、冷然として話を聞いていた。やはり右の手では、右頬にある大きなニキビを気にしながら、である。
そして老婆の話を聞いている間に、ある勇気が生まれてきた。それは先ほど門の下で、この男に欠けていた勇気だ。
そして、先ほど老婆を捕らえたときの勇気とは、真逆に動こうとする勇気である。
「そうか。」
下人は嘲るような声で念を押した。そうして一歩前へ出ると、右手をニキビから離し、老婆の襟首を掴みながら噛み付くように言った。
「では、俺が追い剥ぎをしようとも恨むまいな。俺もそうしなければ、餓死する体なのだ」
下人は、すばやく老婆の着物を剥ぎ取った。足にしがみつこうとする老婆を、手荒く死骸の上へと蹴り倒す。
ハシゴまでは、たったの5歩だ。下人は剥ぎ取った檜皮色の着物をわきにかかえて、またたく間に急なハシゴを夜の底へと駆け降りた。
——しばらく死んだように倒れていた老婆が、その裸の体を起こしたのは、それから間も無くのことである。
老婆はつぶやくような、うめくような声をたてながら、まだ燃えている火の光をたよりに、ハシゴの口まで這っていった。
そうして、そこから、短い白髪をさかさまにして、門の下を覗き込んだ。
外には、ただ黒洞々たる夜があるばかりである。
下人の行方は、誰も知らない。
『羅生門』は、善悪について考えさせられる物語である
羅生門は、ともすれば「わけのわからない物語」だと思われてしまうこともある小説です。かくいう私も、国語の授業で習ったときには「なんだこの物語は」と思ったクチです。
しかしよくよく読んでみると、下人と老婆の心理の移り変わりが巧みに表現され、また場面ごとの読者の心境を「下人の心の移り変わり」という形で上手に描写した物語だと読み取れます。
善悪は、感じる人の視点で変わります。そして一人の人間の中でも、その時々によって変わってゆきます。羅生門は、この「善悪」について考えさせられる物語でした。
青空文庫で無料公開されていますから、原文もあらためて読んでみてはいかがでしょうか。